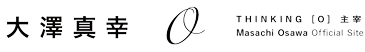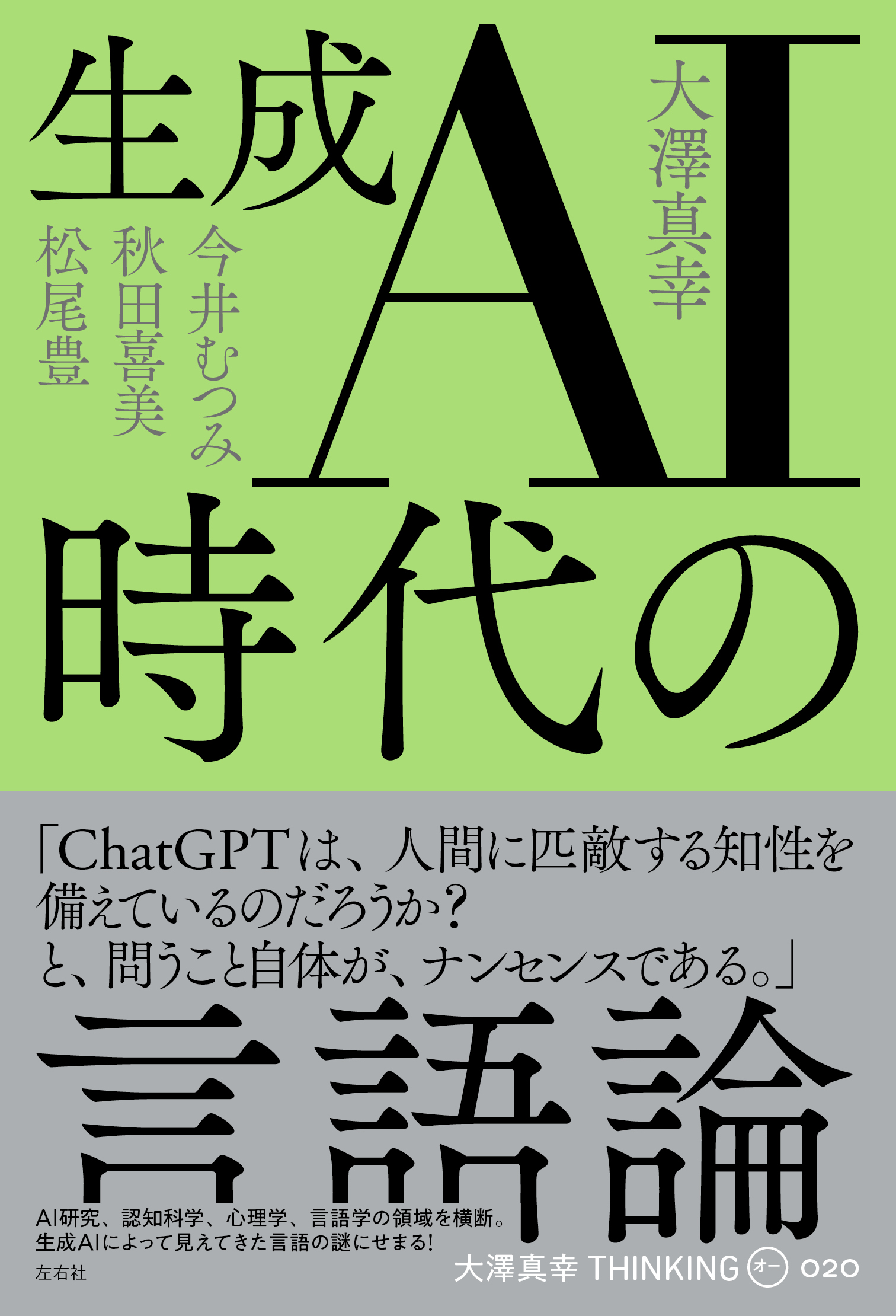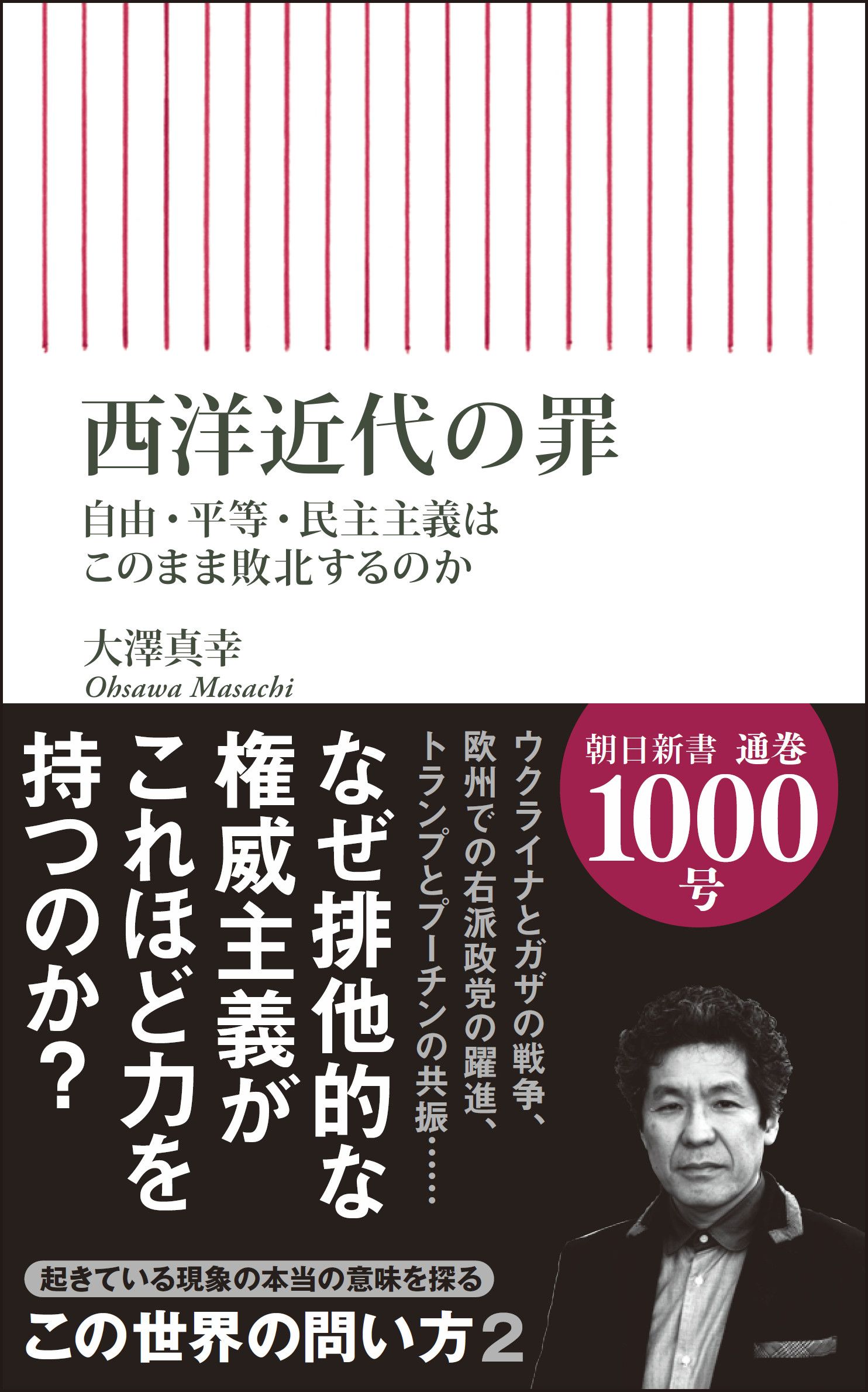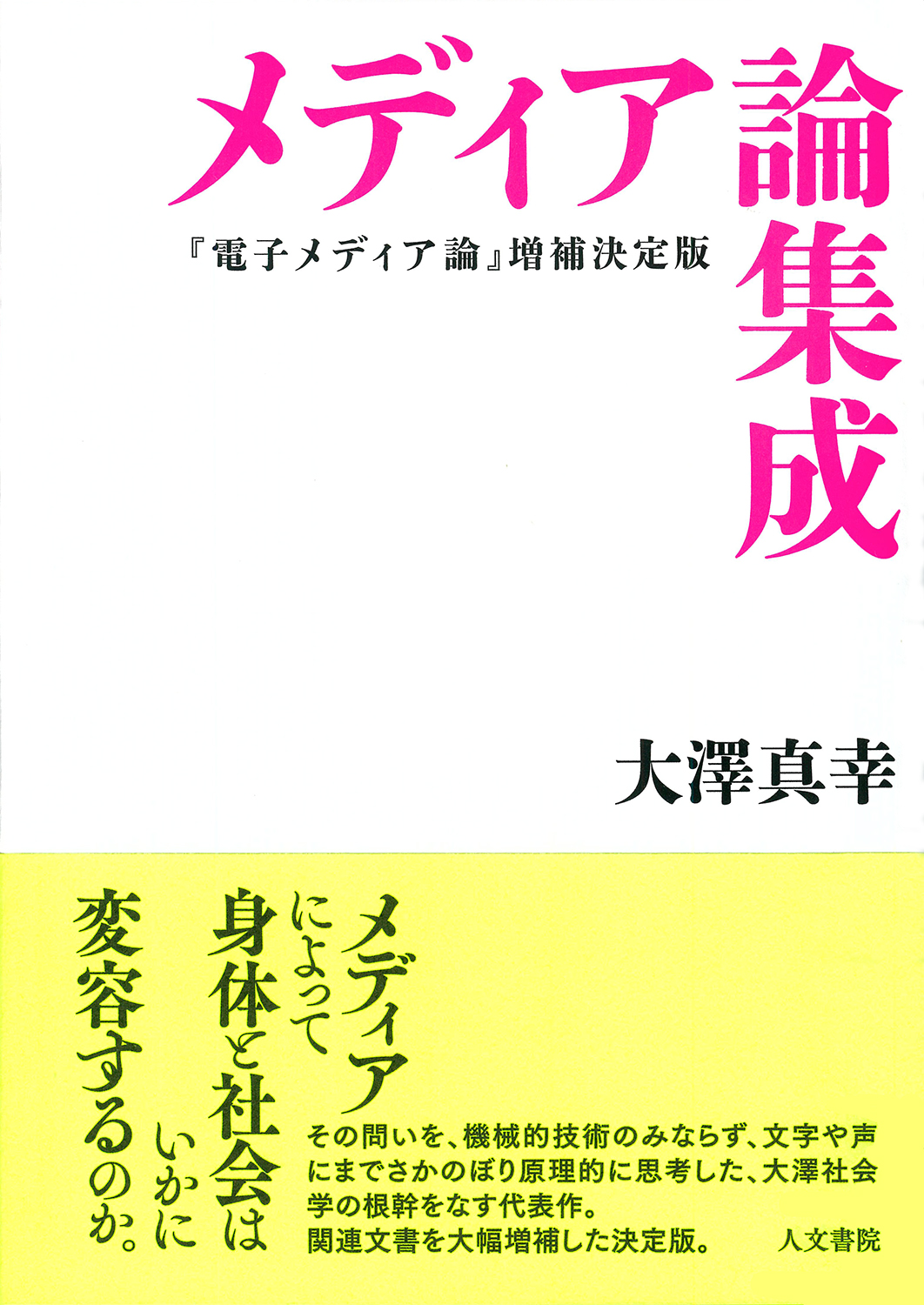ことしから群像新人文学賞批評部門の選考委員に就任した3人、鷲田清一さん、熊野純彦さん、大澤真幸による鼎談「批評とは何か」が、発売中の「群像」2014年11月号に掲載されています。
大澤 シンギュラーなものの中にある普遍性を引き出すことこそ「考える」というしぐさであって、それを言葉にしていくという作業が一方である。それは日本でもどこでもあるわけです。
このことを踏まえた上で、他方で、極東の島国というか、非西洋のどこでもある時期以降、考えるということは西洋の思考様式を輸入しながらなされてきた、という面がある。それは押しつけられたわけじゃなくて、我々は、西洋の中に蓄積されてきた知の伝統というものに惹かれて、すごく魅力を感じてきたのです。それは否定しがたい。
だから我々はそれを輸入しなきゃいけないと考えて、輸入を専門的に担った人たちがかつてたくさんいたし、今でもいる。その中に哲学研究というのも枢要な一部として入っているわけです。他方で先ほど言った、シンギュラーなものからものを考えていく仕事をした人がいて、分業みたいなものができてしまった。でも本来は分業であるべきじゃない。例えば小林秀雄はベルクソンを輸入しながら、しかし同時にある固有の対象について考えるということをしてきたわけです。しかし、両面を区別することなくなしえた人は、小林とか、あるいは大森荘蔵とかごく一部だったということは否めない。
僕が今危惧するのは、その両面はそうはいっても、ある時期まで結構融合していたのに、近年その二つが大幅に分離していることです。哲学研究は今でも盛んに行われているけれども、本当に「研究」なんですね。他方で、西洋やその他の哲学を咀嚼しながら、それと対決するという作業を全く抜きにして批評的なものが出てくる。(略)
熊野 ところでごく普通に考えて、この三人の取り合わせは、文芸誌の選考委員として異様なわけです。もちろん背景は知りませんけれども、たぶん対外的にはものすごいショック療法に見えますよね。ただ、これは恐らく三人が一致できると思いますけれども、文学作品を対象にした、いわゆる文芸評論を拒否するつもりは全くない。先ほどの大澤さんの言葉を転用させてもらえば、そこに単独なものを介して普遍性に向かう鋭い思考の回路が存在するならば、すぐれた評論たり得るだろうし、僕らはそれを十分に楽しむだろうと思うんです。
大澤 結果的に言えば、今までより間口が広くなったと考えていただければいいんですよ。もちろん、いわゆる狭義の文芸評論だっていいわけです。ある種のシンギュラーな出来事性とか、体験とか、霊感とか、そういうものから普遍性へと向かっていくのが思考というものです。かつてはそれは文学と非常に深く結びついていたので、文芸評論ということで思想の主要な部分をほぼカバーできた時期があるんだけれども、だんだん、必ずしも文学と結びついていないところで、やらなければいけなくなっている。文学に触発されて始まったっていいし、ほかのところから、例えばある出来事について考えたものから始まってもいい。ある普遍性へと向かっていく一つの思考様式がそこにあれば。(略)鷲田 (略)
ある言葉でもいいし、出来事でもいいし、どんなものでもいいと思うんだけれども、その小さな穴や裂け目を潜り抜けたものを、既成の座標軸に位置づけるのではなくて、別の領域にいわば斜交的につなげていってほしい。実はこの小さな感受性、あるいはこの小さな出来事のこの表現はこんな意味を持っているんだ、こんな新しいビジョンにつながっているんだということを見せてくれるのが評論かなと僕は思っているんです。一つ一つの文学作品というのは、むしろその小さな出来事をその人ならではの表現で描いている。熊野さんが言ったときめき、ワクワク感というのを僕はそんな風に理解しています。
鼎談の全篇、ならびに評論賞への応募要綱などは「群像」HPなどをご覧ください。
「群像」2014年11月号には、連載評論「〈世界史〉の哲学」第67回も掲載されています。