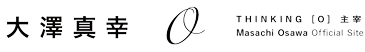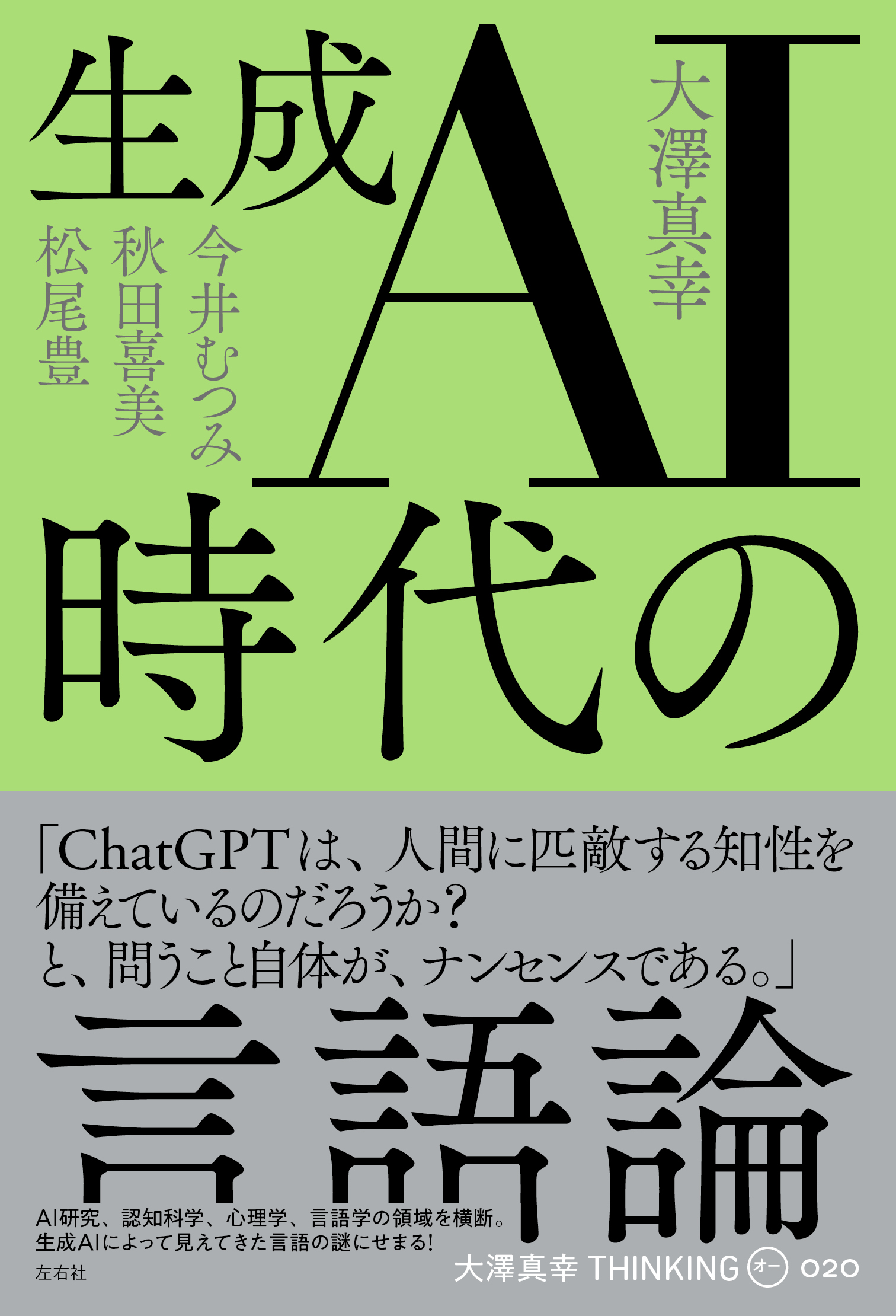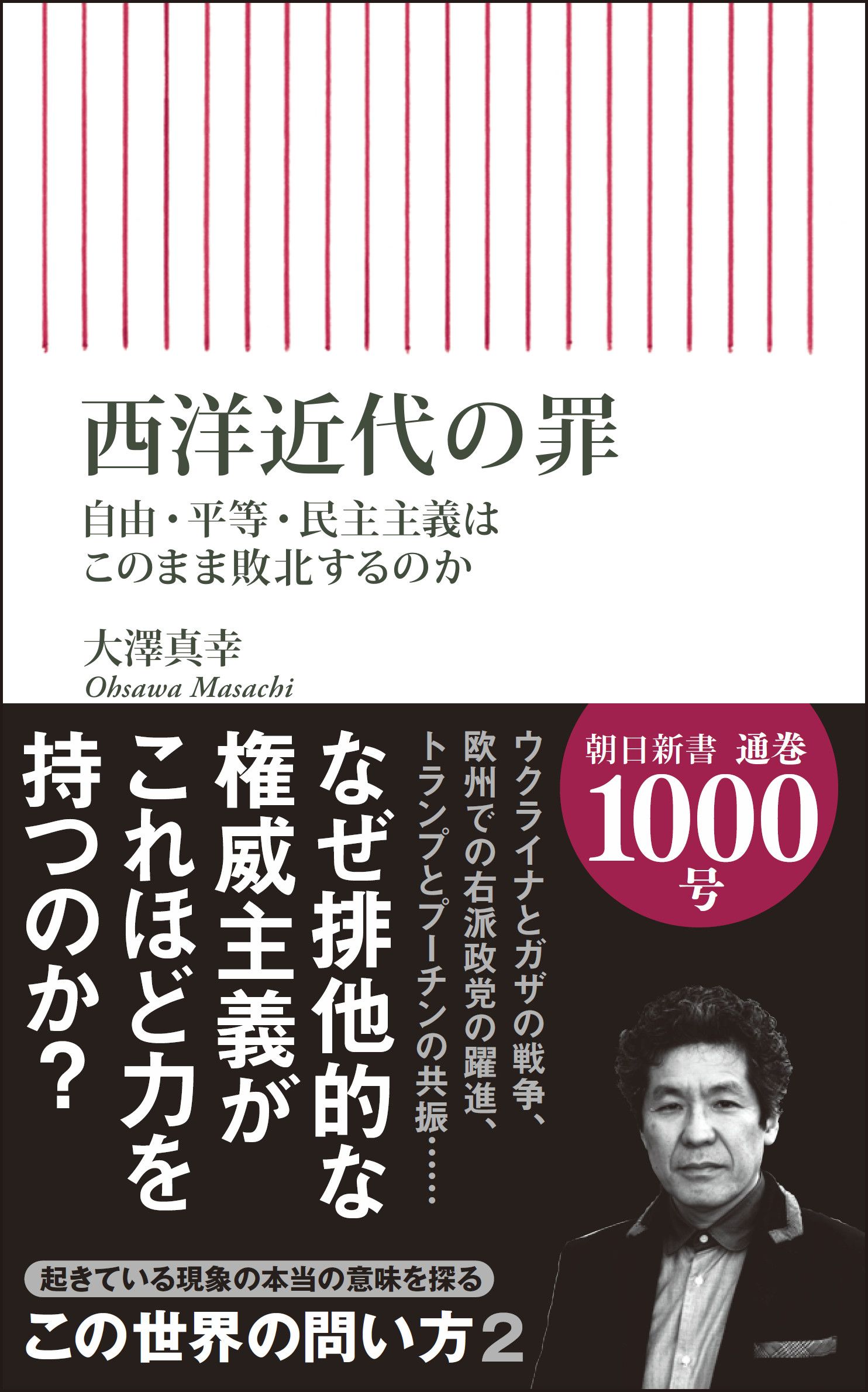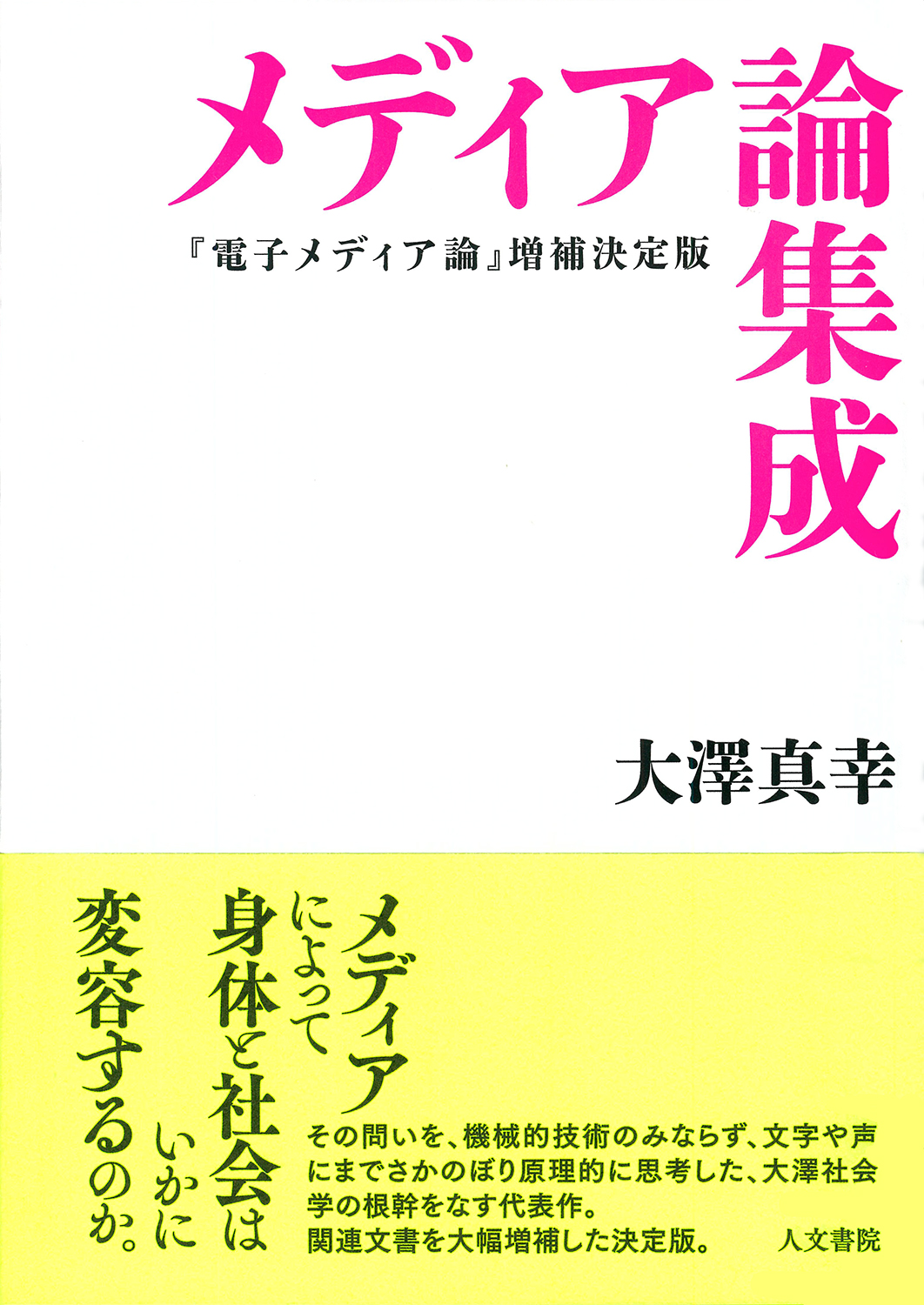図書新聞2012年1月27日号に、『60年代のリアル』(ミネルヴァ書房)を上梓した社会学・佐藤信氏との対談「60年代と現代をつなぐ思想」が掲載されています。
大澤:肉体感覚というか皮膚感覚みたいなものが60年代にあった運動を駆り立てていた最大のエレメントだった、それをベースにしながら、現代の20代の若い人にとって政治とは何かを考え直していく。なぜ佐藤さんは60年代という時代の区切り方をしたのか。そこには根拠が必要だと思うんですね。
佐藤:それまでの枠組みではうまく捉えきれない雰囲気が60年代にはあったんじゃないか。最近では外交文書も開いてきて、実証的な研究もされているんですが、結局は高度経済成長の部分だけが強調されてしまう。これまでの政治学的な分析から疎外されていた部分に注目したかった。
大澤:現代は、既にそうした肉体感覚が失われているところから出発し、そうであるがゆえの、肉体感覚・皮膚感覚へのノスタルジーがある。同じ肉体という問題に対して、「まだあるものが失われる」という局面と「すでにないものを回顧する」という局面で、ちょうど合わせ鏡のような対応関係が出ていると思うんです。そういう意味で、時代の取り方や目の付け所が面白かった。
佐藤:現代と60年代の「リアル」が似ているという前提を置いて、僕の本は書かれています。大澤先生の場合、「現実」というものが変わっているというご認識だと思うんです。その時に、昔は触媒があったからこそ「リアル」なものだったのか、今の「リアル」は、そもそも触媒がないような「リアル」なのか、そこがどういう関係になっているのか。
大澤:あえて言うと、「リアル」は同じものだったと考えた方がいいと、僕は思います。僕らがこれこそ生きていると感じられる、あるいは生きていることと死んでいることの境目にあるような実質を感じられる「リアル」というのは、恒常的で、ユニバーサルな不変項としてあると思う。人が掴みたいのは、それですよね。自分が生きている核に本当は何があるのか。
大澤:「ざわめき」という概念を重視されている。非常にわかりやすいし、変に格好つけたアカデミックな概念よりも訴えるものがある。他方、比喩的拡張力に訴えた議論になっている感じがして、微妙な違和感も覚えました。
佐藤:皮膚というものの明確性を示した上で、その皮膚をざわめかせるものとは何か。この飛躍は、ぼくが、これまで社会学的な側面で書かれてきたことを政治学的な文脈の中に置き換えた時に起こったものだと思うんです。融通の利かない社会と身体とをどう結びつけるか。
長文の対談全編は、図書新聞2012年1月27日号1〜3面に掲載されています。
(上記抜粋中、中略・文意がわかるように改変した部分があります)