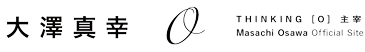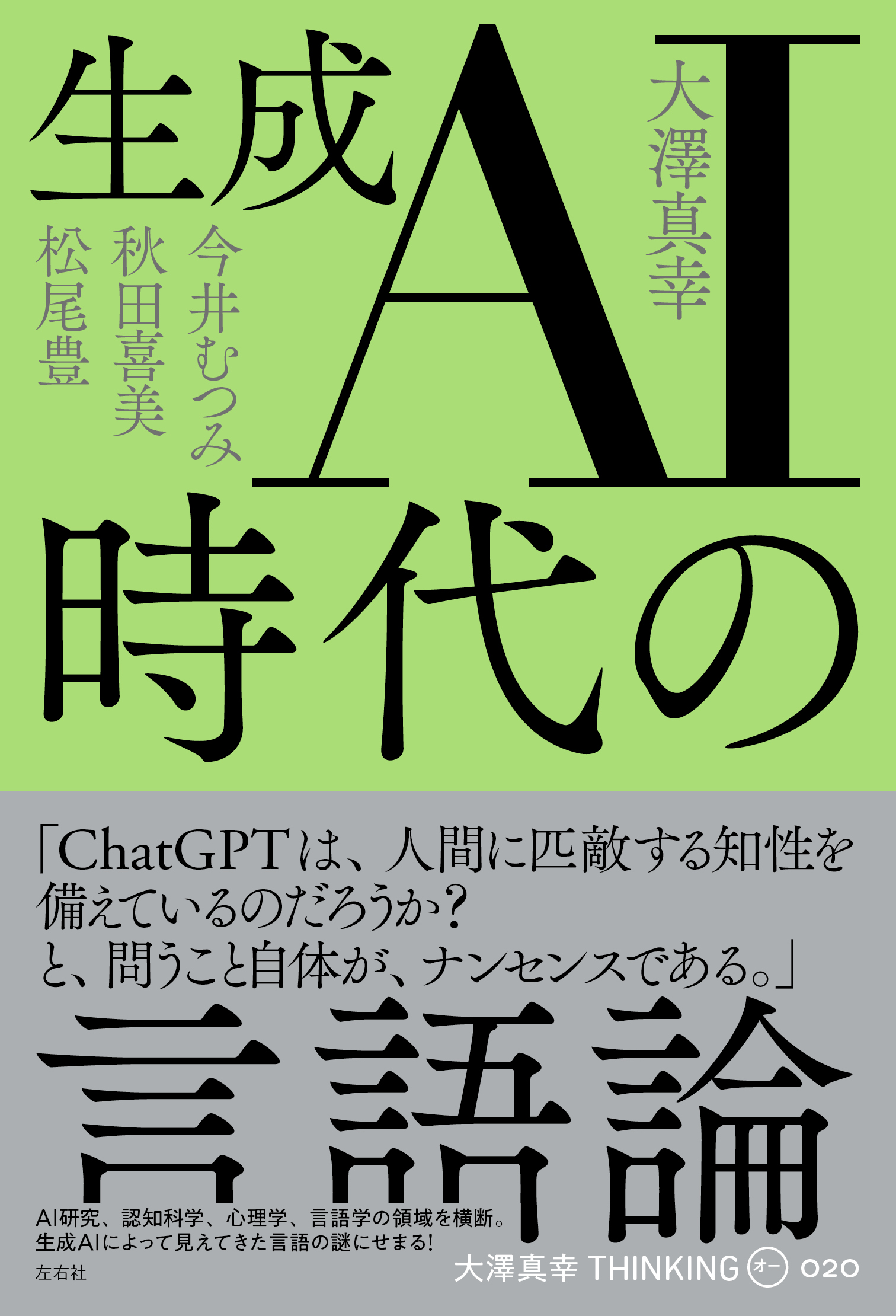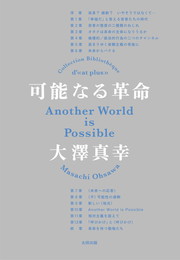朝日カルチャーセンター横浜校で、講義「日本史上ただ一度の革命 社会を変える真因」を行います。
日本史上ただひとり、革命家といえる人物がいる。そのことを新著『日本史のなぞ』で論じました。
このたびの講義では、さらにその思考を深め、なぜ日本では革命が起きにくいのか、いかにすれば革命は可能なのか、世界史をも俯瞰しつつ日本的システムの解析に挑みます。
日本は革命とは無縁の、変えにくい社会だと言われています。大化改新や明治維新といった、幾たびもの大きな社会変動でさえ、外的刺激を通じて変容したのであり、けっして「革命」ではありませんでした。それはなぜなのか。
しかし、日本史上唯一の革命家といえる人物がいます。それは誰なのか。
気鋭の社会学者が、世界史と日本史を俯瞰しつつ日本的システムを精緻に解析し、日本ではなぜ革命が起きにくのか、いかにすれば革命が可能であるのかを解き明かします。そして、新著『日本史のなぞ』の思考をさらに深めて歴史に対峙し、社会を変える真因に迫ります。
※当日「日本史のなぞ―なぜこの国で革命が一度だけ革命が成功したのか」大澤真幸著
(朝日新書720円)を販売いたします。
日 時:2017年1月28日15:30-17:30
受講料:会員3,024円/一般 3,672円(いずれも税込)
会 場:朝日カルチャーセンター横浜教室(〒220-0011横浜市西区高島2-16-1ルミネ横浜8階 TEL045-453-1122)
詳細・ご予約は、朝日カルチャーセンター横浜教室HPからお願いします。