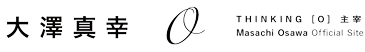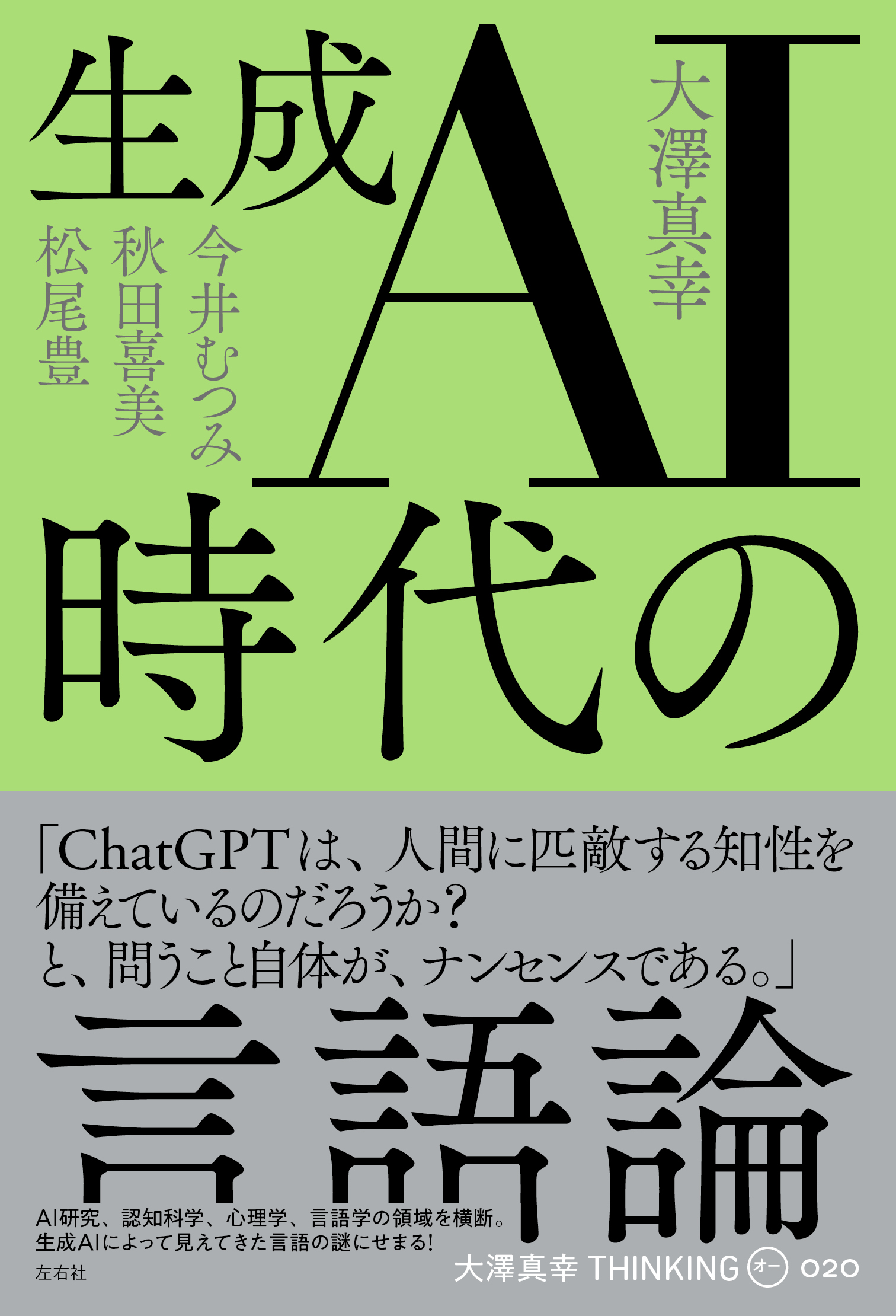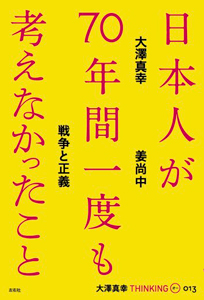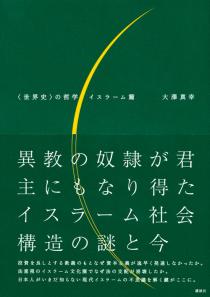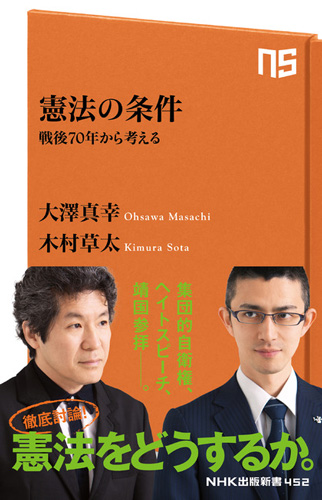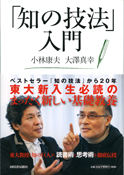有名作品を入り口にして、資本主義社会の“その先”を考える。 (さらに…)
【終了】「現代社会論」次回は1月13日に開講します【1/13】
朝日カルチャーセンター新宿教室にて開催している「現代社会論」。次回は2018年1月13日に開催します。
テーマは「日本」。武士道と現代日本人を考えます。
2018年の始めに、「日本」ということを主題に考えてみたいと思います。このシリーズとしては、やや異色です。
設定したテーマは、武士道はなぜ真逆なものに反転したのか、です。
日本の近代社会は、武士が最終的な勝ち組になっていた社会(徳川時代)を直接の母胎として生まれてきたわけですから、武士のエートス(生活スタイルや考え方)を基盤にしてできあがっているはずです。
武士は、本来、所領の維持・拡大を目的とする戦闘者です。そのエートスは、だから、戦う個人主義です。その個人に所属する総合的な実力だけがものをいう、生(なま)の、過激な個人主義。
ところが、現代の日本人は、個人主義者というよりは集団順応型(たとえば空気を読む)であり、戦闘者とは逆に、戦わずに紛争を処理する技術(たとえば根回ししたり)に長けている。つまり、武士とは正反対の人間像が、典型的な現代日本人。
どうしてこんなことになったのだろう、というのが問題設定。
一コマで語るにはややテーマが大きいのですが、できれば、日本史の最大のなぞ、どうして武家政権が圧倒的に優位にたっても、なお朝廷勢力と共存し続けたのか、という問題にも立ち入ってみたいと考えています。
日 時:2018年1月13日
会 場:朝日カルチャーセンター新宿教室(〒163-0210東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル10階(受付))
参加費:全1回=会員3,024円/一般3,672円(いずれも税込)注意事項 ・詳細なテーマは開講7~3日前にHP、twitter(@asakaruko)にてお知らせします。
・教室、参加費など上記の内容は変わる場合があります。10階と11階の変更もあります。当日の案内表示をご確認ください。
詳細・ご予約などは、朝日カルチャーセンター新宿校HPでも随時告知します。
【終了】現代社会論:コミュニケーションの可能条件【11/11】
朝日カルチャーセンター新宿教室にて開催している「現代社会論」。次回は理論的な内容です。
今回は、久しぶりに純理論的な話をします。
社会学の対象は、コミュニケーションです。テーマは、「コミュニケーションの可能条件」。
具体的な事例を分析しながら、そこから理論的な含意を引き出します。
イギリスに、「沈黙の双子」として知られているケースがあります。この双子は、生まれてから20年あまり、ほとんど話をしなかった。しかし、調べてみると、知能の発達や普通の意味での言語障害はまったくないのです。やがて、双子の間だけでは、会話をしていることがわかってきます(ただ、あまりにもすごい早口で、周囲の人には、ほとんど暗号のようなものにしか聞こえない)。この双子が、思春期になって、奇妙な犯罪(放火など)を繰り返すようになって、世の中の注目を集めました。
なぜ双子は話せなかったのか。どうして、二人だけの間ならば話ができたのか。どうして犯罪をしたのか。
このことから、コミュニケーションはいかにして可能かを考えていきます。
「文化社会学の根本問題」
日 時:2017年11月11日15:30-17:30
会 場:朝日カルチャーセンター新宿教室(〒163-0210東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル10階(受付))
参加費:全1回=会員3,024円/一般3,672円(いずれも税込)注意事項 ・詳細なテーマは開講7~3日前にHP、twitter(@asakaruko)にてお知らせします。
・教室は変わる場合があります。10階と11階の変更もあります。当日の案内表示をご確認ください。
詳細・ご予約は、朝日カルチャーセンター新宿校HPからお願いします。
【終了】大澤聡さんの新刊刊行記念トークイベントに登壇します【10/16】
メディア論、思想史をフィールドとする批評家の大澤聡さんの編著『1990年代論』が刊行されました。その刊行記念イベントに登壇し、著者の大澤聡さんと対談します。
大澤聡編著『1990年代論』(河出書房新社)刊行記念大澤聡×大澤真幸トークショー
「新・現代日本論序説――1990年代以降の社会と思想」1990年代は日本社会の「転換期」だとしばしば指摘される。ところが、当時の政治や経済の状況、様々な出来事、思想潮流などを組み合わせながら、それを正面から検討した先例は思いのほか少ない。あの時代は現代社会にどんな影響を及ぼしているのか――。
70年代以降生まれの気鋭の論者たちを結集した渾身の一冊『1990年代論』を編んだ批評家・大澤聡と、90年代から論壇の第一線で活躍、時代を捉えた思考を紡ぎ続ける社会学者・大澤真幸が、2010年代まで射程を拡張して「現代日本社会」を総括。世代を超えた新たな対話のアリーナがここからひらかれる。日 時:2017年10月16日(月)19時〜
会 場:代官山蔦屋書店(東京)
参 加:『1990年代論』&イベント参加券セット2500円、もしくはイベント参加券1,500円をご予約、ご購入
お問い合わせ:代官山蔦屋書店店頭、もしくはお電話03-3770-2525(1号館1階 人文フロア)にて承ります。
詳細は、代官山蔦屋書店HPのイベント情報をご確認ください。
【終了】「金閣寺」から読み取る三島事件【11/18】
朝日カルチャーセンター横浜教室にて、三島由紀夫をめぐる講座を開催します。
「金閣寺」から読み取る三島事件
三島の最高傑作とされる「金閣寺」。この小説を書いたとき、三島は、十四年後に自衛隊に突入し、割腹自殺することになるとは思っていなかっただろう。しかし、「金閣寺」の主人公による金閣寺への放火は、三島のこの後年の「(失敗した)革命」の美学的な先取りと解釈することができる。
「金閣寺」を読解することを通じて、どうして三島があのような行動を取ることになったのか、その謎を解くことができる。と同時に、三島が「あのようには行動しなかった可能性」への芽も、同じ「金閣寺」の中に見いだすことができる。(講師記)日 時:2017年11月18日(土)15:30〜17:30
会 場:朝日カルチャーセンター横浜教室(〒220-0011 横浜市西区高島2-16-1ルミネ横浜8階TEL045-453-1122)
参加費:会員3,024円/一般3,672円
詳細・ご予約は、朝日カルチャーセンター横浜教室HPからお申し込みください。
【終了】日本箱庭療法学会第31回大会で基調講演を行います【10/7】
日本箱庭療法学会の大会初日のシンポジウムで、「こころの新時代と心理療法」と題して基調講演を行います。
基調講演「こころの新時代と心理療法」
日 時:2017年10月7日(土)13:30〜16:30
会 場:上智大学四谷キャンパス(102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1)6-101教室シンポジストに河合俊雄さん(京都大学こころの未来研究センター)、司会は横山恭子さん(上智大学)です。
第31回日本箱庭療法学会は、10月7日、8日の2日間に渡って開かれます。両日のプログラム、ワークショップの詳細などは、学会HPでご確認ください。
【終了】日本基督教学会第65回学術大会「宗教改革とポスト近代」シンポジウムに登壇します【9/30】
「宗教改革とポスト近代(宗教改革500年を記念して)」を主題に開催される、日本基督教学会でシンポジウムに登壇します。
シンポジウム「宗教改革とポスト近代」
登壇者:大澤真幸氏(社会学者)、江口再起氏(ルーテル学院大学)、深井智朗氏(東洋英和女学院大学)、西原廉太氏(立教大学)、司会:石居基夫氏(ルーテル学院大学)
日 時:2017年9月30日(土)14:00〜16:30
会 場:ルーテル学院大学(東京・三鷹)
参 加:一般参加可能。シンポジウムのみの聴講は500円。
本シンポジウムは、9月29日、30日の2日間に渡って開催される、日本基督教学会第65回大会の2日目最終セッションとして企画されています。研究発表、特別講演(「宗教改革とエキュメニズム、その到達点、課題と展望」テオドール・ディーター氏)などのプログラム詳細は、学会HPからご確認ください。
【終了】奈良県人権部落解放研究集会にて基調講演を行います【9/24】
大和郡山市で開催される、「第44回奈良県人権・部落解放研究集会」にて、「憎悪と愛の弁証法」をテーマに基調講演を行います。
開 催 日:2017年9月24日(日)9:20〜
開 催 地:大和郡山市
参 加 費:3000円(昼食代は含みません)
会 場:DMG MORI やまと郡山城ホール(全体会・分科会会場)プログラム:
【午前】全体会・基調講演
【オープニング】大和郡山市 やまと獅子太鼓
【記念公演】講師:社会学者 大澤真幸さん「憎悪と愛の弁証法」
【午後】分科会・フィールドワーク
第1分科会 「だれもが希望を持って生きられる社会」を
第2分科会 「両側から超える」部落解放運動と私たちの課題
第3分科会 「これからも住み続けられる地域づくり」の展望を
第4分科会 講演形式
①「部落差別の解消の推進に関する法律」とこれからの人権教育・啓発について
②今まで語れなかった家族とハンセン病
③『社会の中で 輝ける人に』~自分にしかできないことがあること気づいていますか?~
詳細は、奈良人権部落解放研究所HPをご確認ください。
【終了】憲法学者の木村草太さんとトークします【9/14】
いま起きている衝撃的な事件や出来事。これを長い時間軸の中で、理論的に考えてみるとどうなるか? 木村草太さんと検討します。
「近代」から現代社会を考える 社会学と憲法学から
今起きている衝撃的な事件や出来事は、時事問題として観察する対象であるだけでなく、 長い時間軸の中で、理論的に考えてみるべきものでもあります。
今回の対談では、大澤先生の「<わたし>と<みんな>の社会学」を踏まえ、「近代」という構想の淵源と射程を考えながら、現代の社会について検討してみたいと思います。(木村草太)日 時:2017年9月14日19:00-20:30
会 場:朝日カルチャーセンター新宿教室(〒163-0210東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル10階(受付))
参加費:会員3,456円/一般 4,104円(いずれも税込)
詳細・ご予約は、朝日カルチャーセンター新宿校HPからお願いします。
【終了】北田暁大さんと文化社会学をめぐってトークします【9/9】
朝日カルチャーセンタ新宿教室にて、社会学者の北田暁大さんを講師に開催される、講座「文化社会学入門 解題「社会にとって趣味とは何か」」。その第1回目のゲストとして登壇します。
「文化社会学の根本問題」
日 時:2017年9月9日18:30-20:00
会 場:朝日カルチャーセンター新宿教室(〒163-0210東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル10階(受付))
参加費:全4回=会員13,392円/一般15,984円。1回のみ=会員3,456円/一般 4,104円(いずれも税込)
詳細・ご予約は、朝日カルチャーセンター新宿校HPからお願いします。
「新しい文化社会学の方法の基準」を打ち立てることを目指す全4回の講座には、他に、小川豊武さん(昭和女子大学講師)、寺地幹人さん(茨城大学講師)、工藤雅人さん(文化学園大学助教)、岡沢亮さん(日本学術振興会特別研究員)、團康晃さん(大阪経済大学講師)などが登壇します。詳細は、上記のHPをご確認ください。